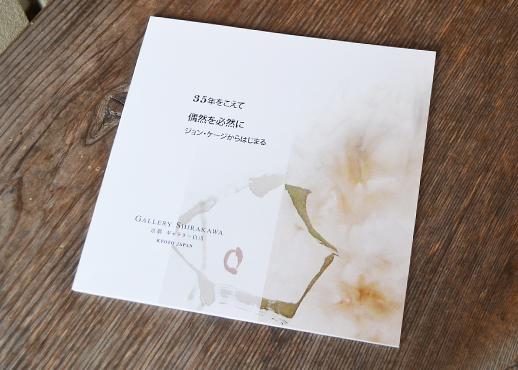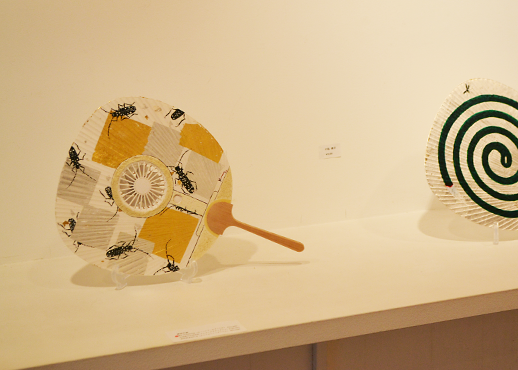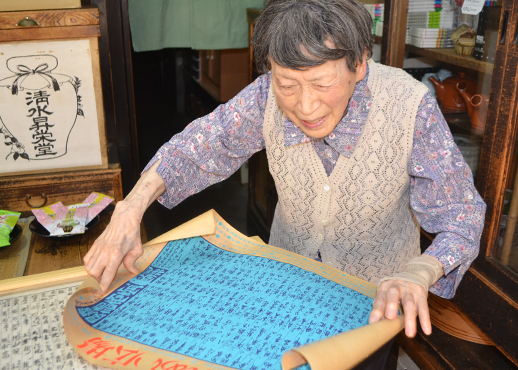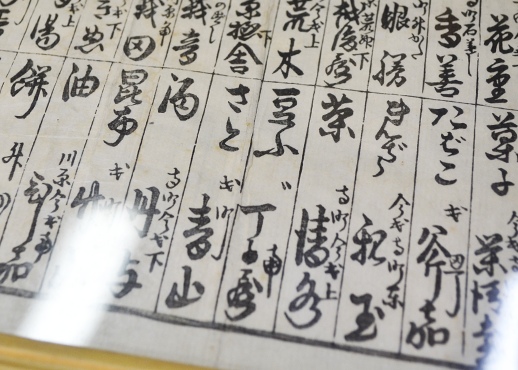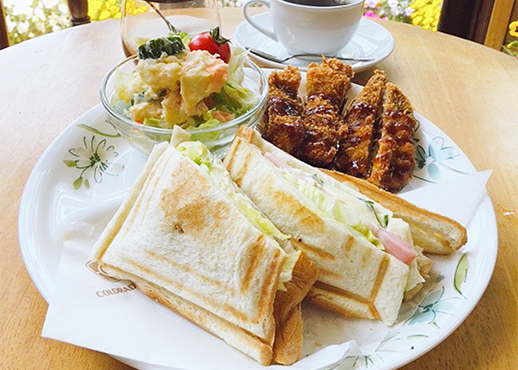大徳寺の近く、新大宮商店街の一画にあるパン屋さんは、釣り竿のかわりに麦の穂をかついだ、えびすさんの看板が目印です。
レーズン酵母を自家培養し、国産小麦と沖縄の塩、湧き出る清水のような水だけで、ゆっくりゆっくり時間をかけて作るパンは、独特の香りと噛みしめるほどに感じる豊かな味わいにおどろきます。大切に「育てる」ようにして作るパンを「パンたち」と慈しむように語る、今年で開店満20年の「えびすやのパン」藤原雄三さん、嘉代子さんの、仲睦まじいお二人に話をお聞きしました。
サラリーマン時代からあたためていた夢

藤原さんは、サラリーマンだった時、定年後の第二の人生をどのように生きていくかを模索していたと言います。環境汚染やアレルギーの子どもが増えるなど、様々な問題が起きていました。そして「これからはスピードや大量生産を競うのではなく、もっとゆっくり時間をかけて安全安心の食生活を大切にし、自然の恵みをいただくことに感謝する時代に、きっとなる」と感じたそうです。
だれもが安心して食べられる安全な食品が大切だと考え、無農薬の農業をやろうと思い立ちました。ところが嘉代子さんに相談すると、賛成してもらえませんでした。なぜか「虫が苦手やから、ちょっとなあ」ということで農業は断念し、では何かと考えた時にひらめいたのがパン作りでした。

それからは独自に研究を重ね、あちこち材料をさがし、多くの素材を試し研究しました。そのなかで出会ったのが現在も使い続けている「北海道産小麦はるゆたか」「天然のおいしさの回帰水」「ミネラル豊富な沖縄の粟国(あぐに)の塩」です。そして培養するレーズン酵母は4日ほどかけて発酵させ、液をしぼり、小麦粉をまぜて約一日おいて天然酵母となります。

えびすやのパンは、このように小麦粉、水、塩、レーズンの4つの材料だけで作られています。「レーズン酵母、小麦粉、水、塩はそのままでは食べられないが、それぞれの特徴を引き出して、人がちょっと手助けをしてやればパンに生まれ変わる。素材も人もお互いに生きている。ゆっくりした時間とはこういうことだったのか」と、10年くらいした時、パンを作りながら、ふと気がついたと語ります。
「それは一生懸命作ってきたからこそ、そこに到達できました」と続けました。雄三さんのパン作りは、生き方や人生に対する考えそのものです。
「長く続けて」とお客さんからの声援

えびすやのパンがある新大宮商店街は、大徳寺の近くにある南北に長い商店街です。西陣織の伝統産業に携る職人さんの日々の暮らしを支えてきた商店街として、今も多くのお客さんが来やすく、世間話をする光景をよく見かけます。
えびすやも、おなじみのお客さんが多く「がんばって長く続けてや」と声援が送られています。あかちゃんのいる若いおかあさんからも「安心して離乳食にできる」と喜ばれています。

雄三さんは「パンたち」を作る時、いい子や、いい子や。おおきに、ありがとう」と声をかけていると言います。条件を整えてやれば、ちゃんとふくれてくれる、いい子たちなのです。「たまに手順や発酵の時間を間違えても、ちゃんとふくれてくれる。そういう時は、こっちのミスをカバーして、ふくれてくれて辛抱強い子やなあ。おおきに、おおきに」と、自然に感謝の気持ちがわいてくると続けました。
安全安心の素材との共同作業です。「発酵のスピードなど、その日その時によって違う。同じことはない。いつも違って難しいから、ものづくりはおもしろい」と、本当に楽しそうな表情です。

雄三さんは、今年の1、2月に入院しお店を休みました。退院後の静養中もいろいろと思案をめぐらせ、研究しました。これまでは仕込んだ次の日の朝に必ず焼かないとならないと思ってやってきましたが「一日冷蔵庫でねかせたらどうなるか」とテストをし、その結果「ちゃんと焼けた。うちのパンはすごい。ありがとう」という結果を得ることができました。
冷蔵で休んでもらう一日ができたことにより、体がとても楽になったそうです。「作っていける期間が伸びたかなあ」と、お客さんとの「長く続けて」という約束も果たせるでしょう。

今、原材料費が高騰しています。ことに酵母にもレーズンパンにも使っているカルフォルニア産のレーズンはすさまじい高騰が続いているそうです。仕入れ分が終わった時、どうするか。大変な難題が突き付けられています。雄三さんは、サイズを小さくしたりレーズンの量を減らすことはしたくないと、その点ははっきりしています。価格の変更は止むを得ないけれど、高くなった値段でお客さんはどうかなど、いろいろと考えています。
今、あらゆる食材の値上げや内容量を減らすなどが始まっています。こういう時こそ、作り手、売り手、そして私たち消費者が協同して乗り越える時だと思います。えびすやのパンもきっと、雄三さん嘉代子さん二人と、お客さんの歩み寄りで解決していけると感じています。

余った生地で作るかわいいパンをいただきました。わずか4センチ足らずの極小サイズながら、ちゃんと「あんぱん」です。食玩ではないのです。「ちびちゃん」と呼ばれて子どもたちにも人気です。ここにも、材料は無駄せず、あそび心を感じるパン職人としての雄三さんの気質が垣間見られます。
パンは夫婦二人からのメッセージ


えびすやのお店は、以前5年ほどパン作りを手伝っていた方が描いた、気分が明るくなる花の絵が飾られ、カウンターのショップカードや小物もかわいらしくディスプレーされています。嘉代子さんのやさしい雰囲気を思わせます。窓際にパンが並び、小さなカウンターの向こう側は、さえぎるものはなく、そのまま厨房になっています。オープンキッチンではあるのですが、こんなにオープンな店舗兼厨房は他に例を見ないのではと思うほどです。

最初からオープンキッチンにしたと思っていたかをたずねると、きっぱり「最初からです。小麦粉の袋、生地をこねる様子、大きなオーブン、すべてを見て知ってほしいと思っていたので。見られて困ることも、困るところも一つもありません」と堂々とした答えがかえってきました。
利益や効率を優先したら、自分が思っていることとは違ってしまう。開店した時からのこの覚悟と言うか、信念があったからこそ、4つの素材だけのパンを世に出すことができたのだと思いました。「やっていることは利益や効率最優先とは、真逆のことやから」と優しい口調できっぱり語りました。雄三さんの手の指は太くがっしりしていて、長年生地をこねてきたことにより、力の入る方向へ曲がっています。この手が20年間、えびすやのパンを作ってきたことを何より雄弁に物語っています。

今、お二人は「第三の人生のステージ」をどうするか相談しているのだそうです。できるだけ長くの声に応えてがんばるけれど、いつかは第2ステージも終幕になる。それはさみしい、悲しいことではなく、次の新たなスタートになるのです。
雄三さんは「安心して食べられるパンで、みんなに喜んでもらえて、第2の人生の選択はまちがっていなかった」と何回か口にされ「パンは夫婦二人のメッセージやなあ」と続けたのです。その確かな実感を持って、第3の人生を話し合っているのだと感じました。「えびすや」の名前は嘉代子さんの旧姓「胡(えびす)」からとったとのこと。このお店へ来た人がえびす顔になり、パンを食べてまたえびす顔になる、そんなイメージがわいてきます。
お二人の写真を撮らせてくださいとお願いした時、けがをして歩行が少し不自由になった嘉代子さんに何度も「ゆっくり来たらええから、ゆっくり」と声をかけていました。その姿は夫婦であり、まさにえびすやのパンの同志でした。奇をてらわず、おもねず、正直に焼くパンが、これからも多くの人の心も体もやさしく健やかにしてくれることを願ってやみません。
えびすやのパン
京都市北区紫野門前町45
営業時間 9:00~
定休日 日曜、月曜、木曜